2009年03月06日
焼き物は~こうなって~こうなります。
今日はお天気も良く気持ちいいですね~☆
風はマダマダ冷たいですが、日差しはポカポカでチップ(犬)も伸びて寝ています
さて今日の大日窯は釉薬をかけたり修正をしたり、窯に積んだりとバタバタやってます
そこで、焼き物がこうなって~こうなるというのをUPしちゃおうかと思います^^
私は有田に住んでいながら、お嫁にくるまで焼き物がどうやって出来るか全然知りませんでした(恥)
ですが焼き物に携わるようになって、焼き物はおくが深いなぁ~とかロクロって見た目簡単そうだけど神業だな~とか。
色々な事を日々感じ勉強させていただいてます^^
焼き物が出来るまで~大日窯嫁の簡単説明^^;
①生地を土で作ります。
(生地の作り方も色々あるんですが省略させていただきます^^;ながーくなるので、また次回ご紹介できればと思います。)
②生地を乾燥させて柔らかかった土を硬くします^^
(クッキー位の硬さって言うんでしょうか^^)
③削って形を整えます!
鉋を使い高速な回転台の上にのせて削るので粉が結構飛びますっ 削る時は必ずマスクをしないと、たまに口の中がザラザラと…
削る時は必ずマスクをしないと、たまに口の中がザラザラと… 私がどうやら口を開けて削ってるみたいです^^;
私がどうやら口を開けて削ってるみたいです^^;
集中すると口が開いてるんですよね^^;
④水拭きをします!
削った生地を柔らかいスポンジや布で拭いていきます。ここの状態で生地がキレイになっているかチェックしながら丁寧に拭いていきます。拭き終われば数時間置いて水分をとばします(乾燥)
⑤窯に入れて一度素焼きします(900℃)
素焼きすれば、ある程度硬くなるので扱いやすいです^^←私的に^^;

↑絵付け風景です。
⑥絵付けをします。絵付けの前は生地を一度キレイに掃きます。素焼きの後は粉(生地の)が生地についています そのまま絵付けするとカッサカサでかけないのでキレイに粉を掃い、キレイになった生地に絵付けします
そのまま絵付けするとカッサカサでかけないのでキレイに粉を掃い、キレイになった生地に絵付けします

↑釉薬をかける前。絵付けの写真の物とチョット違いますがご了承ください
⑦釉薬をかけていきます。
釉薬?!とは焼き物の表面のピッカピカのガラス質にする物です。
コレを素焼きの生地に付ける事によって本焼きした時にキレイな焼き物になるんですよ^^

↑釉薬です。生地に釉薬をかける時は~よく混ぜます!!こんな風に混ぜ混ぜ×②
粉を水に溶かしたものなので、短時間で沈殿し始めちゃうんです

釉薬をかける時は~こんな風にスルリ~ッと生地を釉薬の中にくぐらせます!!
私は調子に乗ってスルリ~ッポチャッ!!っと生地を落としてしまうので夫の担当です^^

釉薬(大日窯は釉薬も原料から昔ながらに調合して作っています。)をかけ終わった物がコレです!キレイなお化粧をしたみたいに真っ白になります^^
手触りは、サラサラです!少し時間をおいてさらに乾燥させると、もっとサラサラに
サラサラになった生地に最終チェックで修正していくのは私の担当です!!
修正の達人?!っと言ってます^^←私だけ。。水拭きも達人です^^;
⑧窯に積んでいきます。
慎重に慎重に・・!おもーーーい板をのせながら積んでいきます!

↑この板が重い 「軽量で~割れないで~曲がらない板のあったらよかとに~」っとブチクサ言いながら積んでます^^;
「軽量で~割れないで~曲がらない板のあったらよかとに~」っとブチクサ言いながら積んでます^^;
積み終わったら準備完了!!
⑨本焼きです。
(1300℃)で焼いていきます。夫の腕の見せどころです^^
っと言うのは、大日窯の窯は電気窯じゃない手動のガス窯なので一時間ごとに炎をチェックしないといけないんです 泊まりこみの作業になります
泊まりこみの作業になります お疲れ様です
お疲れ様です
本焼きが終わり100℃位に窯の中の温度が下がればとりだします 毎回緊張しちゃいます^^;
毎回緊張しちゃいます^^;
⑩出来上がり!っと言いたいところですが、上絵がある焼き物はその後上絵付けをしてまた窯に入ります!!
上絵(赤絵)は850℃弱で。上絵によって温度は違うんですが、大日窯の赤絵は無鉛のためこの温度で焼きます。
こうなって~こうなって~焼き物って出来ているんです
わたし流で(嫁)サラリとお話ししてみました^^;
もっとおくが深いのですが・・・。

本日午後5時に本焼きはじめました
16時間~17時間で焼成終了です
頑張れ~!っ!
夫が只今焼成中ですっ^^ちょっと様子を見に工場へ
さて明日は保育園の餅つき大会です
夫も「オイも行きたかった~!! 」
」
っとスゴク悔しがってます
代わりに私が美味しくいただいてきます
風はマダマダ冷たいですが、日差しはポカポカでチップ(犬)も伸びて寝ています

さて今日の大日窯は釉薬をかけたり修正をしたり、窯に積んだりとバタバタやってます

そこで、焼き物がこうなって~こうなるというのをUPしちゃおうかと思います^^
私は有田に住んでいながら、お嫁にくるまで焼き物がどうやって出来るか全然知りませんでした(恥)
ですが焼き物に携わるようになって、焼き物はおくが深いなぁ~とかロクロって見た目簡単そうだけど神業だな~とか。
色々な事を日々感じ勉強させていただいてます^^
焼き物が出来るまで~大日窯嫁の簡単説明^^;
①生地を土で作ります。
(生地の作り方も色々あるんですが省略させていただきます^^;ながーくなるので、また次回ご紹介できればと思います。)
②生地を乾燥させて柔らかかった土を硬くします^^
(クッキー位の硬さって言うんでしょうか^^)
③削って形を整えます!
鉋を使い高速な回転台の上にのせて削るので粉が結構飛びますっ
 削る時は必ずマスクをしないと、たまに口の中がザラザラと…
削る時は必ずマスクをしないと、たまに口の中がザラザラと… 私がどうやら口を開けて削ってるみたいです^^;
私がどうやら口を開けて削ってるみたいです^^;集中すると口が開いてるんですよね^^;
④水拭きをします!
削った生地を柔らかいスポンジや布で拭いていきます。ここの状態で生地がキレイになっているかチェックしながら丁寧に拭いていきます。拭き終われば数時間置いて水分をとばします(乾燥)
⑤窯に入れて一度素焼きします(900℃)
素焼きすれば、ある程度硬くなるので扱いやすいです^^←私的に^^;

↑絵付け風景です。
⑥絵付けをします。絵付けの前は生地を一度キレイに掃きます。素焼きの後は粉(生地の)が生地についています
 そのまま絵付けするとカッサカサでかけないのでキレイに粉を掃い、キレイになった生地に絵付けします
そのまま絵付けするとカッサカサでかけないのでキレイに粉を掃い、キレイになった生地に絵付けします

↑釉薬をかける前。絵付けの写真の物とチョット違いますがご了承ください

⑦釉薬をかけていきます。
釉薬?!とは焼き物の表面のピッカピカのガラス質にする物です。
コレを素焼きの生地に付ける事によって本焼きした時にキレイな焼き物になるんですよ^^

↑釉薬です。生地に釉薬をかける時は~よく混ぜます!!こんな風に混ぜ混ぜ×②
粉を水に溶かしたものなので、短時間で沈殿し始めちゃうんです


釉薬をかける時は~こんな風にスルリ~ッと生地を釉薬の中にくぐらせます!!
私は調子に乗ってスルリ~ッポチャッ!!っと生地を落としてしまうので夫の担当です^^


釉薬(大日窯は釉薬も原料から昔ながらに調合して作っています。)をかけ終わった物がコレです!キレイなお化粧をしたみたいに真っ白になります^^
手触りは、サラサラです!少し時間をおいてさらに乾燥させると、もっとサラサラに

サラサラになった生地に最終チェックで修正していくのは私の担当です!!
修正の達人?!っと言ってます^^←私だけ。。水拭きも達人です^^;
⑧窯に積んでいきます。
慎重に慎重に・・!おもーーーい板をのせながら積んでいきます!

↑この板が重い
 「軽量で~割れないで~曲がらない板のあったらよかとに~」っとブチクサ言いながら積んでます^^;
「軽量で~割れないで~曲がらない板のあったらよかとに~」っとブチクサ言いながら積んでます^^;積み終わったら準備完了!!
⑨本焼きです。
(1300℃)で焼いていきます。夫の腕の見せどころです^^
っと言うのは、大日窯の窯は電気窯じゃない手動のガス窯なので一時間ごとに炎をチェックしないといけないんです
 泊まりこみの作業になります
泊まりこみの作業になります お疲れ様です
お疲れ様です
本焼きが終わり100℃位に窯の中の温度が下がればとりだします
 毎回緊張しちゃいます^^;
毎回緊張しちゃいます^^;⑩出来上がり!っと言いたいところですが、上絵がある焼き物はその後上絵付けをしてまた窯に入ります!!
上絵(赤絵)は850℃弱で。上絵によって温度は違うんですが、大日窯の赤絵は無鉛のためこの温度で焼きます。
こうなって~こうなって~焼き物って出来ているんです

わたし流で(嫁)サラリとお話ししてみました^^;
もっとおくが深いのですが・・・。

本日午後5時に本焼きはじめました

16時間~17時間で焼成終了です

頑張れ~!っ!
夫が只今焼成中ですっ^^ちょっと様子を見に工場へ

さて明日は保育園の餅つき大会です

夫も「オイも行きたかった~!!
 」
」っとスゴク悔しがってます

代わりに私が美味しくいただいてきます


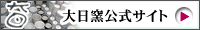
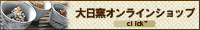








ブログだけではもったいない、ショップサイトにも載せちゃいましょうよ^^
プロの技。
想像してたのとは全然違いました^^;
なんかハイテクな感じがします。
ん~確かにこんなにまとめて撮ったのは・・・(汗)
ありがとうございます。。
みんなで協力して製作しています。
なかなか手間隙かかりますし、うまくいかない事も(笑)
でも、そこも楽しいんですヾ(o・ω・)ノ゚.
はい。最後の写真が窯(ガス窯)の写真ですよ。。
ハイテク!?
想像されているのは・・・登り窯では!?
本当に ショップサイトに載せて
広く 日本中のお客様に見てもらったらいいよ~
すばらしいです
手が込んでいます
しかし 大日窯さんは 値段が安いから
元とれますか~?
心配です・・・
窯屋をやっている弊社のホームページにそのままコピーして使わせていただきたいほどです。
それから、登り窯や薪の窯の見た目をご存知の方にとっては、ガス炉や電気炉はハイテクな感じに見えるようですね。昔のおもちゃ、「ゴールドライタン(知りませんか・・・?)」的なゴツゴツ、カクカク感がありますからね。
確かにいつも簡単な記事なので^^;(笑)
大作なんて・・・お恥ずかしいです^^;
全く焼き物の事を知らない方もこんな感じなんだーっと、少しでも興味をもってもらえたら嬉しいなぁっと思いUPしました。
あくまで私流なので^^;簡単なんですが^^;
私も昔は窯といえば登り窯が頭の中に浮かんできていた気がします^^
ガス炉や電気炉は窯元などに行かないと目にしないので、窯のイメージは登り窯が強いですよね^^
ゴールドライタン?!
ガンダム??!!
本当に日本中の方に大日窯を知ってもらいたいです^^
ここ数年はガス代も上がり大変ですが、多くの皆様に使っていただきたいので頑張ります!